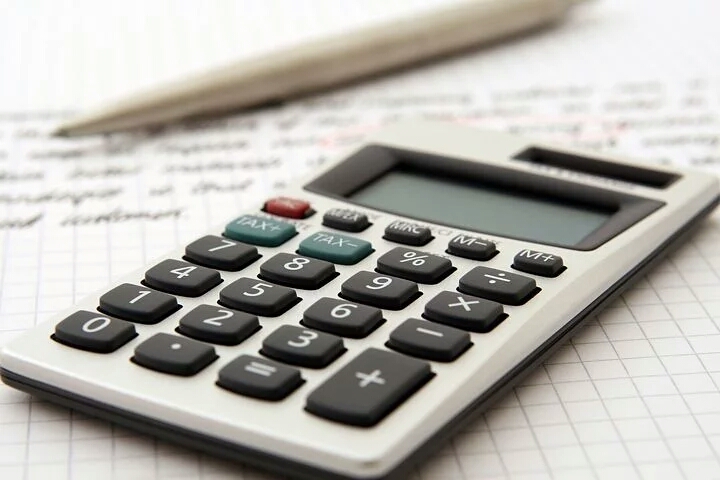変化の激しい時代において、トレンドと言われるものの移り変わりも非常に激しくなっています。
世の中の変化の1つとしてキャッシュレス化がありますが、各業界が生き残っていくためのDX戦略というのが近年、注目されています。
というわけで今回は「キャッシュレス時代を生き抜く業界のDX戦略」について詳しく説明致します。
キャッシュレス時代を生き抜く業界のDX戦略①【日本のクレジット会社の現状】

「キャッシュレス時代を生き抜く業界のDX戦略」というテーマで1つ目に取り上げるのは「日本のクレジット会社の現状」です。
2020年を境として様々なことが世界へ変化を及ぼしています。
コロナ禍という状況が与えたインパクトは非常に大きく、様々な業界に多大な影響を及ぼしました。
非接触ということが大きなテーマとなり、ビジネスは新たなニーズを生み出すと共に、新たな価値観を植え付けていくことになったのです。
様々なオンラインサービスの登場やリモートワークなど、大きな変化が起こり、これまで基準とされてきた常識さえも大きく変わっていきました。
変化の1つとして、日本のキャッシュレス化というのも、ここ一年で急加速していきました。
このキャッシュレス化は、「国策」であり、政府が積極的に推進していることの1つなのです。
消費者還元事業やコード決済事業者等によるポイント施策というのも積極的に行われており、ポイント還元バトルが行われているのです。
コロナ禍という状況が生み出した「非接触ニーズ」というのもキャッシュレス化にとっては、勢いを加速させる追い風となったのです。
日本国内のクレジットカード事業者においては、基幹システムを構築することにより、自社の戦略に応じた独自サービスを展開するというのが一般的なやり方でした。
ですが、キャッシュレス化が進んだことにより、収益性が低い決済については、基幹システムにおいては、今のニーズに応えられないというのが現状なのです。
クレジットカード事業者に求められるのは、コスト削減、はらには、これまで以上のサービス提供、クレジットカードを利用すべき新たな付加価値を消費者に与えていくことでした。
新たなサービスを開発している間にも、キャッシュレス化の波は加速していくわけですから、開発そのものの短期化というものも同時に求められるようになってくるのです。
このように、業界によっても様々なことで、解決すべき問題点というのが生じてくるわけです。
実際のところ、クレジットカードの在り方というのは、どうなんでしょうか。
インターネットが発展したことによってグローバル化が進み、市場もまたそれに応じてグローバル市場となりました。
そのような現代社会のグローバル市場において日本のクレジットカード決済というのは、高コストなのです。
それ故に起こり得る様々な問題というのが生じてくるわけです。
日本政府が積極的に推し進めているキャッシュレス化です。
キャッシュレス時代を生き抜く業界のDX戦略②【キャッシュレス化の進捗度】

「キャッシュレス時代を生き抜く業界のDX戦略」というテーマで2つ目に取り上げるのは「キャッシュレス化の進捗度」です。
「キャッシュレス元年」と言われたのは、時代が1つの区切りとなった令和元年でした。
日本の決済市場というのは、実に様々なキャッシュレスサービス事業者が新サービスを一斉に開始したのです。
キャッシュレス化への大きな時代の流れに影響を受けたのは、クレジットカード事業者でした。
キャッシュレス化そのものについては、クレジットカード事業者にとってもプラスのことではありましたが、その一方で少額取引の増加による影響は、少なからず受けることになったのです。
少額取引が増加すれば、単価そのものは低下するわけですから、コストは増えるわけです。
影響を受けるのは、クレジットカードを利用する消費者ではなく、加盟店であり、手数料というコストがかかるわけで、従来通りの収益構造では、上手くいかないことが課題として明確になっているのです。
これまでの日本のクレジット業界全般に対する見方として、諸外国と比較してもコスト的には高いと言われています。
その背景にあるのは、自社で基幹システムを構築し、メンテナンスを行い運用していることにあります。
つまりシステムを維持するためのコストが必要であり、その分、コストとしての負担が大きくなってしまうということになるのです。
そのような事情はあるにせよ、時代というのは変化していくわけでAPIやAIなどの活用と共に、業界全体がデジタル化に傾いていることを鑑みれば、企業としても投資せざるをえないという事情もあるのです。
デジタルシフトが加速している時代において、企業においての積極的な投資というのを行わなければ、グローバルスタンダードとしてのビジネス戦略に基づくような、競争力という意味でも失いかねないのです。
積極的な投資というのは、決して守りの投資ではなく、長期的な戦略を考慮した攻めの投資となり、企業としては、内部のみならず外部に対しても積極的な投資ということを示すきっかけにさえなるのです。
今、日本のクレジットカード事業者というのは、ある意味、分岐点に置かれています。コスト構造変革を真剣に捉え、改善していくことを避けては、決して通れない段階に差し掛かっているのです。
高コストの根本的要因となる、各事業者独自の保有する基幹システムというのを業界全体で抜本的な変えていく必要性があるのです。
キャッシュレス時代を生き抜く業界のDX戦略③【日本と世界の差】

「キャッシュレス時代を生き抜く業界のDX戦略」というテーマで3つ目に取り上げるのは「日本と世界の差」です。
クレジットカード決済コストの高止まりというのが、日本のクレジットカード事業者における根本的な要因であることは、紛れもない事実であり、これを解決しないことには、クレジットカード事業者においては、明るい未来は待って射ないわけです。
日本独自のネットワーク事業者の中には、様々なサービスを展開しており、より支払いやすい数多くの選択肢を持てるようなサービス展開をしているのです。
ボーナス払いや分割払いという方法は、従来までの手法たして、すっかり認知されていますが、実は、支払い方法は日本独自の支払方法なのです。
このような支払い方法のバリエーションは、顧客のためといいつつ、実は事業者側の都合だったりもするのです。
業界全体の課題というのは、改善すべき点が実に多く各事業者が保有する「基幹システム」の都合が大きく関係しているのです。
世界でも共通にクレジットカードというのは、存在するものの日本とのそれとは、事情が全く異なっているようです。
欧米諸国においては、特にシステムにおいての差別化というのは、競争領域ではないのです。
欧米では、TPPが台頭しているのです。
TPPとは、「Third Party Processer:競争領域ではない事務処理などの業務を引き受ける第三者」のことを言います。
複数のクレジットカード事業者のシステムを受託することにより、システム開発を業界全体として行い、業界全体が効率化をはかっているのです。
共同利用という意味では、日本とは全く異り、業界全体が整備されているような強い印象を受けるのです。
日本のクレジットカード業界においては、いかに無駄が多いかがわかります。
コストのシェアリングという意味では、非常に優れた仕組みが構築されていますが、日本独自の業界が整っている現在では、欧米を真似しようとしても、現実的には非常に難しいことがわかります。
日本では、各事業者がそれぞれ独自に基幹システムを構築していることは、それぞれがそれぞれにコストを抱えていることになります。これこそが、根本的な問題となり、思い切った業界全体の抜本的改革が必要となるのです。
大規模きなシステム投資だけでなく、規模が大きくなるということは、それに比例して運用コストも増加するわけで、単純に収益を圧迫することになります。
日本のクレジット業界というのは、委託切替えが焦点となっているわけですが、競争原理を崩すことは難しいのです。