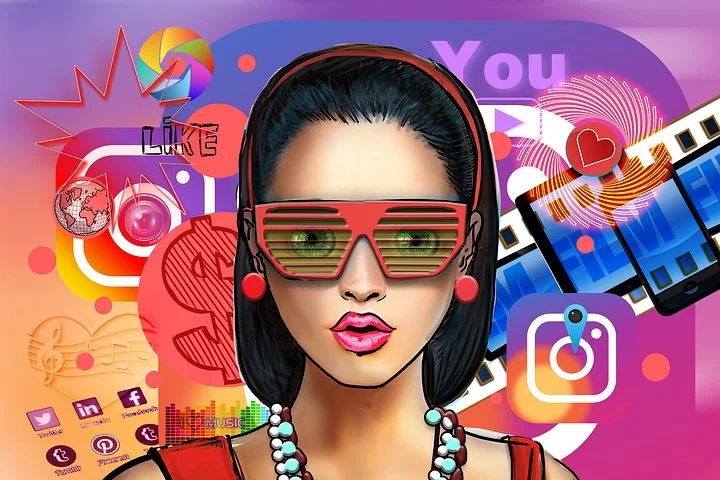ありとあらゆる情報がいたるところに溢れている情報社会。
デジタル化が進む今、デジタルネイティヴが消費行動とマーケティングについて考察していきます。
というわけで今回は「デジタルネイティヴの熱中消費とマーケティングへの依存」について詳しく説明致します。
デジタルネイティヴの熱中消費とマーケティングへの依存①【デジタルネイティヴは、もはや主流】

「デジタルネイティヴの熱中消費とマーケティングへの依存」というテーマで1つ目に取り上げるのは「デジタルネイティヴは、もはや主流」です。
あらゆる情報が世の中に蔓延っている今、私達は、それらの情報に一喜一憂し、時に振り回されていると言っても過言ではありません。
現代において、情報というのは摂取するだけではなく、自ら発信することも簡単にできる時代となりました。
情報社会というのは、受信側と発信側が存在するわけで、デジタル化社会は、そんな双方が形成していきます。
様々なデータというのは、時間が経過すればするほど、新たなデータが発生し蓄積されていきます。
1分1秒を待たずに世界中の誰かがどこかで、データを更新しているのですから、考えてみてみれば、デジタル化がこれだけ進んでいることは脅威としか思えません。
しかし、デジタルが複雑なのか?どうかと言えば、それは単順に異なります。
複雑にしているのは、人間でありあらゆるデータを有効にカテゴライズし分析できていないから、複雑に感じてしまうということなのです。
デジタルそのもので考えれば、0か1しかなく非常にシンプルとなるのです。
そのような様々な要素や現状の中で、デジタル社会というのは、歩みを止めることなく発展していきます。
なぜなら、それを支えているのは、デジタルネイティヴの存在があるからです。
デジタルネイティブというのは、デジタルに対し全く抵抗感がない世代のことを言います。
既に生まれた時から、インターネットやPC、スマートフォン、タブレットなどネットワーク環境やデジタルデバイスが当り前に存在し環境的に整っている世代のことを言います。
デジタルネイティブというのは、その世代全般を指し示すが、さらにカテゴライズすると、以下のように分類されています。
- Z世代: 15~24歳
- ミレニアル世代:25~34歳
このように言われています。
インターネットのコンテンツなどでも、時折、「Z世代」や「ミレニアル世代」という言葉が使われているのを見かけたことがあるのではないでしょうか。
デジタル世界の最先端を行くデジタルネイティブというのは、独自の価値観をもち、その価値観によって消費行動も大きく変わっています。
確かにデジタルネイティヴと言われる存在がいる一方で、その真逆となるアナログ世代も、存在しているわけですから。
どれだけスマートフォンが普及し、ネットかま当り前となった時代においては、それらとは全く無縁に生きている人もまだまだ存在しています。
パソコンやスマートフォンですら、一度も触れたことはなく、インターネットを使ったことすらない方だって存在しているのです。
環境面や状況、価値観というのは非常に大きく差があるからです。
世代間のギャップというのは、想像以上に全く違ってくるのではないかと感じるのです。
デジタルネイティヴの熱中消費とマーケティングへの依存②【デジタルネイティヴの価値観】
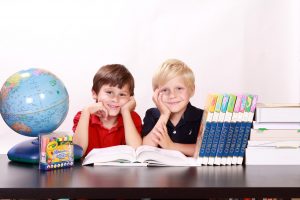
「デジタルネイティヴの熱中消費とマーケティングへの依存」というテーマで2つ目に取り上げるのは「デジタルネイティヴの価値観」です。
さて、デジタルネイティヴの持つ価値観とは、具体的には、いったいどのようなもの?なのでしょうか。
デジタルネイティブは、特に好きなものに対しては、とことん追求するという消費の価値観があります。
デジタルネイティブにとっての「好きなもの」。
これは、単に「好き」という好みの問題だけではなく、自分自身の自己表現であり、個性を出すためのものでもあるのです。
あえて自分という個性を消費にダイレクトに反映させているのです。
個性は1つのアイデンティティであり、その個人を現す象徴と言っても過言ではありません。
インターネットが登場したことにより、コミュニケーションの形というのも大きく変わりました。
いつでもどこでも誰とでも繋がれる、そんな時代だからこそ、個人(個性)を主張し、自分自身をわかってもらい賛同してくれる存在価値というのが非常に大切になったのです。
自らの存在価値の証明というのは、そもそもなぜ必要なのでしょうか?
それは、人間には共存共栄が必要だからです。
人とのコミュニケーションにおいて、実は「個性」というのは、とても大切なこととなります。
デジタルネイティヴというのは、一見自己中心的であり、自己ニーズが満たされれば、それで良いという一方的な見方があるのかもしれませんが、実はそうではなく、周りの目というものを気にするのです。
周りにどう見られているかということは、言いかえれば他人に対し自己表現がしっかりできているかどうか?ということになり、そのことを強く強く意識し考えているのです。
これは、デジタル化が進んだ現代だからこその、この世代の考え方として定着していったものとなります。
デジタルネイティヴの熱中消費とマーケティングへの依存③【デジタル時代のマーケティング課題】

「デジタルネイティヴの熱中消費とマーケティングへの依存」というテーマで3つ目に取り上げるのは「デジタル時代のマーケティング課題」です。
企業にとってのマーケティングの大きな課題といえば、いかにして効果的なマーケティングを行い、顧客を効率よく獲得することができるか?ということです。
この課題はどこの企業も抱えているような共通している課題と言えますが、ここの問題点となるのが、単なる顧客とのコミュニケーションというわけではないのです。
企業がデジタルネイティヴと言われる若年層と関係性を構築し強固にしていくのは、あらゆるデジタル領域上での速やかな対応が、まずは求められるというわけです。
効果的なマーケティングを行うためには、企業内における各部署の連携をより深めることです。
それぞれの部署が的確に顧客の接するためには、企業内での明確なルールと目標が必要となります。
それぞれの目標、つまりKPIを統合することが必要であり、そのために必要となるのが企業内部におけるデジタル基盤となります。
これが、デジタルトランスフォーメーション(DX)と言われるものとなります。
デジタルネイティブへの対応=企業のDX推進という構図が描けるわけです。
デジタルネイティヴというのは、単なる若年層というだけでとらえていては、消費者の印象は、随分変ってきます。
確かに若者の全てが、デジタルネイティヴに当てはまるかというとそうではありませんが、デジタルネイティヴ以前の世代に比べれば感覚的には平均的に優れているのです。
だからこそ、若年層の全てに対しデジタルメディアやデバイスをサービスとして準備しておくことは、ビジネスの基盤としてのインフラ整備のようなものと認識しておくべきではないでしょうか。
既にデジタルネイティヴにとっては、当り前と認識されているェアリングやサブスクリプションなどは、ビジネスモデルとして、しっかり確立されています。
そのようなデジタル社会の時代背景と共にデジタルネイティブへの理解を深めることが今後の企業活動における大きな指針となるのではないでしょうか。
デジタルネイティブをどう捉えていくか、企業の捕え方によって将来的な業績を大きく左右することになっていくのではないでしょうか。
現実的なところで言えば、コロナ禍という状況は、デジタルネイティヴ以外も含め、多くの人のライフスタイルに影響を与えたことは言うまでもありません。
より一層、時代は、デジタルシフトに傾いており、その傾向は強まるばかりとなります。
はたしてデジタルシフトが本当に日々を便利にするのでしょうか?しかし、その流れは誰にも止められません。