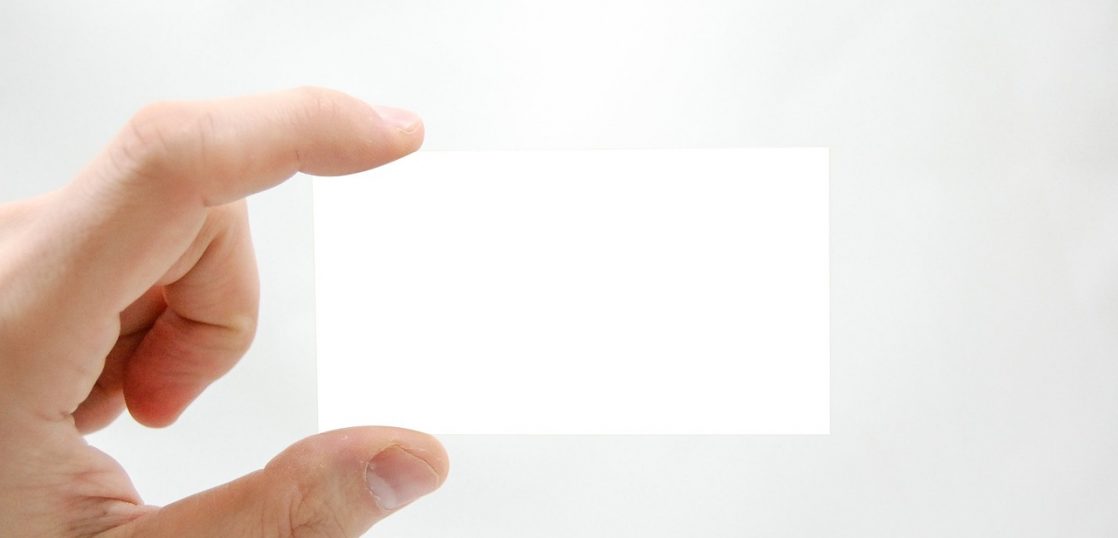ECサイトの存在価値が高まっている現代において、様々な商品を販売する場合、景品表示法に注意する必要があります。
不当表示とみなされないようなサイト運用が必要なのです。
というわけで今回は「不当表示に注意せよ!ECサイト運用で欠かせない!景品表示法」について詳しく説明致します。
不当表示に注意せよ!ECサイト運用で欠かせない!景品表示法①【景品表示法とは?】
「不当表示に注意せよ!ECサイト運用で欠かせない!景品表示法」というテーマで1つ目に取り上げるのは「景品表示法とは?」です。
皆さんが数ある商品の中から選択する決め手とは、いったい何がありますか?
1つの商品にしても無数の数が存在する今、消費としても選択の幅は非常に多岐にわたることになります。
選び放題という状況は、消費者にとっては喜ばしい状況とも言えますが、はたして消費者は、それで本当に幸せなのでしょうか?
もしかしたから、本当のニーズには到達できない可能性だって多いにあるのです。
世の中には、類似商品ばかりが数多く存在しているという事実もあるのです。
そうした中、消費者として商品を購入するための手段として情報を集めることになりますが、情報そのものもまた膨大な量があるため消費者としては、まず判断材料の多さに戸惑ってしまうのです。
そんな消費者の商品選択要素として実際に大きく影響を及ぼすのが価格や特典、そして景品表示などです。
消費者にとっても、売り手にとってもオムニチャネルが増加することにより需要度を増すのが「ECサイト」ではあります。
ECサイトは、カスタマイズや集客の自由度が高いというメリットがある分、実店舗以上に気を付けなければならない点が非常に多いのです。
売り手が注意しなければならないこととして「景品表示法」があります。
様々ある法律の中でも皆さんも耳にしたことがある決まりではないでしょうか。
しかし、実際には、この景品表示法とは具体的には、どのような法律なのか詳しく理解されている方も少ないのではないでしょうか。
景品表示法の正式名称は、「不当景品類及び不当表示防止法」です。
目的としては「一般消費者の利益保護」となります。
つまり、この法律は売り手から買い手を守るための法律なのです。
法律で消費者を守ってくれる決まりがあるというのはなぜか?
それは世の中には過大表示というものが実は多いからです。
具体的には景品付き販売によっての不当な利益を上げるケースがあるからです。
実際に消費者というのは、弱い立場にあり売り手から騙されてしまうことも非常に多いのです。
質の高くない商品を購入させられてしまうということも多々あり、消費者が不利益を招くことを防止することを目的とすることと、事業者を規制することが、この法律の目的なのです。
つまり買い手のみではなく売り手側や市場や業界全体をも保護していることになっているのです。
不当な表示や景品による販売が増加することにより、明らかに消費者の目にとまることは多くなるのです。
そうなると消費者が不当表示に該当する商品を購入するケースは、どうしても多くなるわけです。
こうなると、不当表示以外の正当な商品まで含まれてしまい、結局は市場全体が淘汰されてしまうという、好ましくない状況になってしまうのです。
景品表示法は、このような事態を避けることにより、市場のクオリティそのものをキープするという機能も満たしているのです。
公正な競争を保護するという意味では、非常に意味ある法律だと言えるのです。
不当表示に注意せよ!ECサイト運用で欠かせない!景品表示法②【景品表示法に違反すると】

「不当表示に注意せよ!ECサイト運用で欠かせない!景品表示法」というテーマで2つ目に取り上げるのは「景品表示法に違反すると」です。
では、次に景品表示法に違反してしまったら、いったいどのようになるというのでしょうか?
景品表示法違反の疑いがあった場合には、消費者庁が当該事業者に対し事情聴取などの調査を行うことになります。
調査により違反行為が認定された際には「措置命令」が行われることになります。
措置命令に従わない場合には、罰則が適用されることになります。
また違反のおそれがあると判断された場合にも「指導」という形で消費者庁からのアクションがあります。
いくつかの要件を満たしてしまうと課徴金の納付が命じられるというケースもあるのです。
ECサイトの運用に大きく関わるのが「景品表示法」なのか?ということを理解する必要があるのでしょうか?
ECサイト運用においては、商品を購入してもらうための手段として様々な工夫をします。
というのも今やネット上では様々な商品が取り扱われるとともに無数のオンラインショップが存在するからです。
消費者としては、欲しいものがあった時、スマホで検索すれば、非常に多くの購入先がヒットするからです。
ネット上でも商品説明の工夫や値引き、割引、キャンペーン、ノベルティなど、あの手この手で消費者に選んでもらえるような策を行うのです。
ネットショップの魅力というのが、自由な運営やカスタマイズが可能なことなのです。
顧客のためだと考え企画したとしても、やり過ぎはNGとなってしまいます。
「行き過ぎた表示」というものが景品表示法に違反してしまうかもということを意識する必要があるのです。
また気をつけなければならないのは、ECサイトのみではなくSNSによる表示にも気をつけなければならないのです。
懸賞なども景品表示法の対象になりえるのです。
特に現代では、実店舗を持たず販売経路としてオンラインショップのみで運営しているという企業も数多く存在しています。
ネットショップを本格展開する際には、景品表示法についての理解を深めることが基本として必要になるのです。
景品表示法の目的条文の第1条に定義されていますが景品表示法では大きく分けて次の2項目を禁止しています。
- 不当表示
- 不当な景品類の提供
これにより顧客の誘因を防止しています。
商品やサービスの品質、内容、価格等を偽り表示を行うことを厳しく規制していることと過大な景品類の提供を防止するという目的があります。
消費者の自主的で合理的な購買行動そのものを守っているのです。
不当表示に注意せよ!ECサイト運用で欠かせない!景品表示法③【景品表示法の表示の対象範囲と事例】

「不当表示に注意せよ!ECサイト運用で欠かせない!景品表示法」というテーマで3つ目に取り上げるのは「景品表示法の表示の対象範囲と事例」です。
では、具体的に景品表示法に該当するような不当表示とみなされる表示とは、いったいどのようなものがあるというのでしょうか。
事実とは違うことを表示しているということになります。
不当に顧客を誘引するということになるわけですが、これが消費者の商品購入において「合理的な選択を阻害する」ことになれば「不当表示」とみなされてしまうのです。
では、具体的な表示種類について説明していきましょう。
次の3つがあります。
- 優良誤認表示
- 有利誤認表示
- 二重価格表示
では、それぞれについて詳しく説明していきましょう。
1. 優良誤認表示
効果、機能、品質など商品について偽りのある表示。
実際には使われていない成分を表示させることや、確かでな効果を表示することになります。
根拠のない効果を強調するなど、キャッチフレーズとして使用したことが実際にはアウトだったりします。
2. 有利誤認表示
価格、その他の取引条件についての偽りのある表示。
価格が一律表示が前提であると事前提示しているにも関わらず、先着限定割引と偽りの表示をすることが該当します。
常時販売商品を期間限定、個数限定など「限定」とすることが有利誤認表示に該当してしまいます。
3. 二重価格表示
商品を通常価格から値引き販売しようとする場合、現在価格と過去価格を併記する二重価格表示。
具体的には500円→300円と、表記自体は割引しているものの実際には、500円で販売されていた期間がないことです。
つまり比較対象額の500円での販売そのものが嘘ということになるのです。
比較対象額が曖昧ということもあり、根拠のない市場価格と比較することも不当表示とみなされるのです。
比較対象額が元値であると認められる根拠というのも、実際には、そもそも消費者からすれば判断は難しいところとなります。
このような販売表示は、ネット上では、非常に多く溢れているらです。
そのため「販売実績」についてのルールというものが実は定められているのです。
次のようなルールがあります。
- 販売開始から過去8週間の内、4週間以上の販売実績
- 販売した最後の日から2週間が経過していない
販売実績として認められる範囲としての基準は上記となります。
つまり比較対象額での販売は「2週間」となります。
比較対象額での販売実績が実際にあったしても値引き開始から2週間が経過すれば「不当表示」に該当してしまうということを注意しておく必要があるのです。
このように不当表示に該当してしまうというパターンは、意外にも多くに当てはまってしまうということを認識したいただけたでしょうか。
ネット表示では、非常によく見る消費者へのアピール手段となりますが、取り決めとしては、実はギリギリだったりするということがありえるのです。
販売側が「注意する」ということが、必要以上に注意しないと該当してしまうことになるのです。